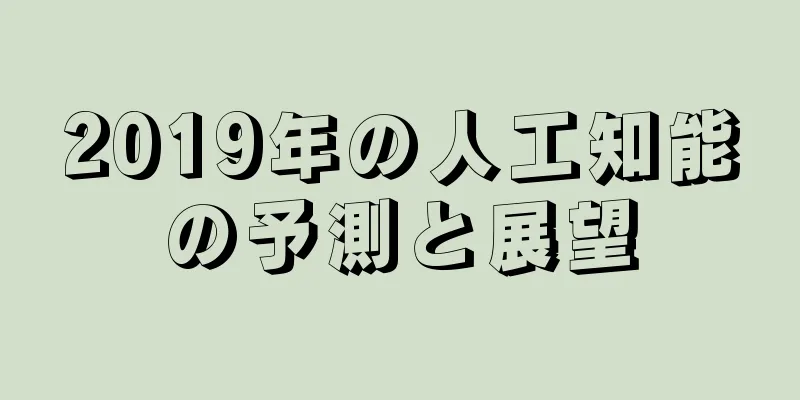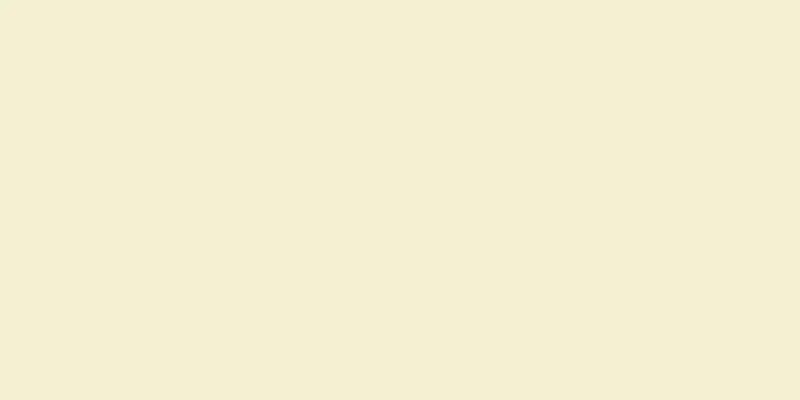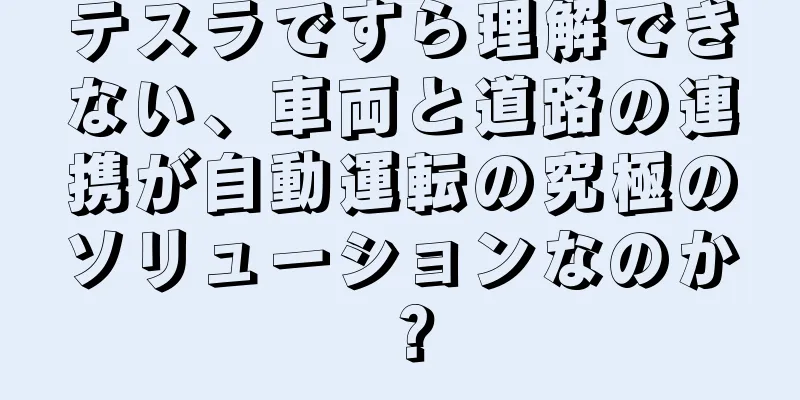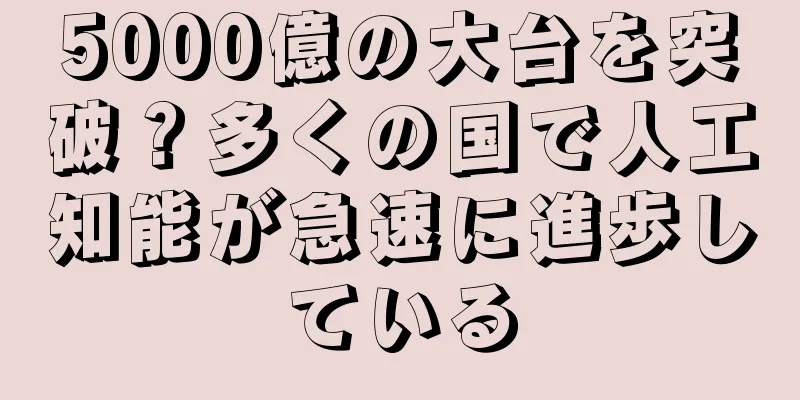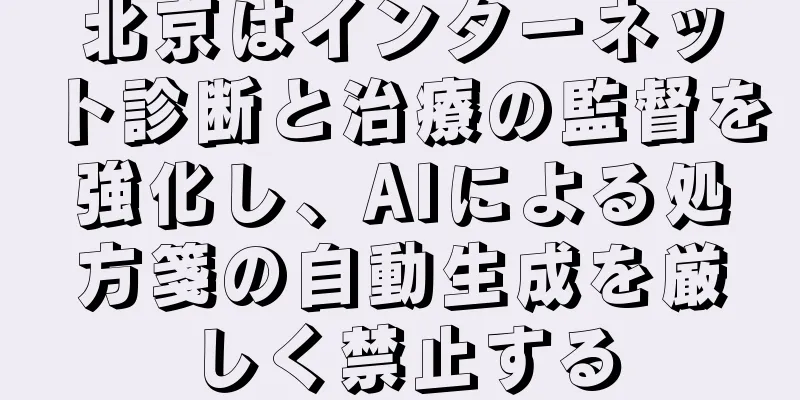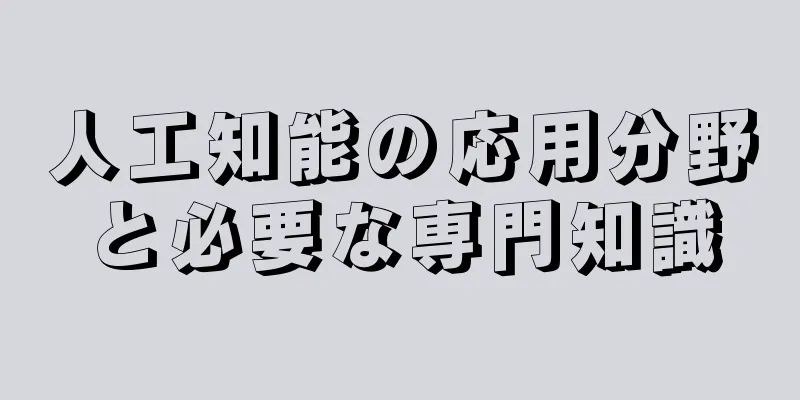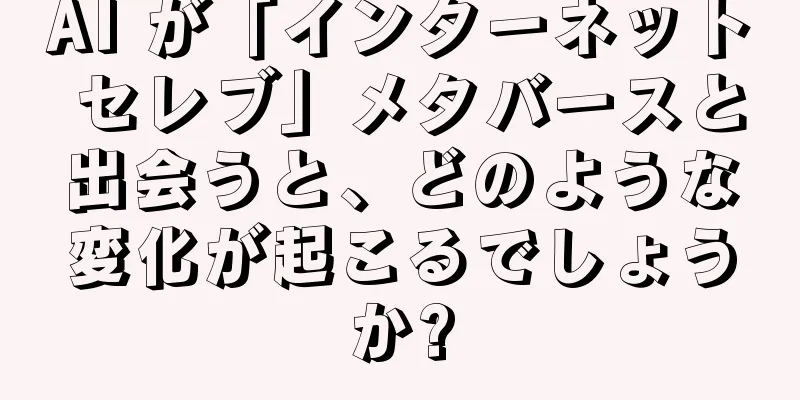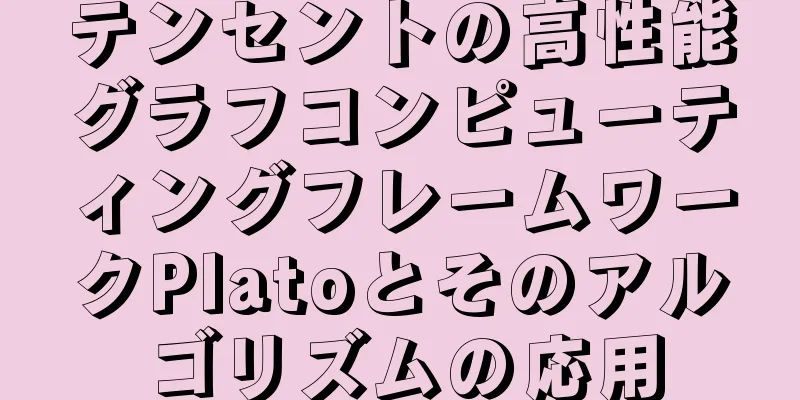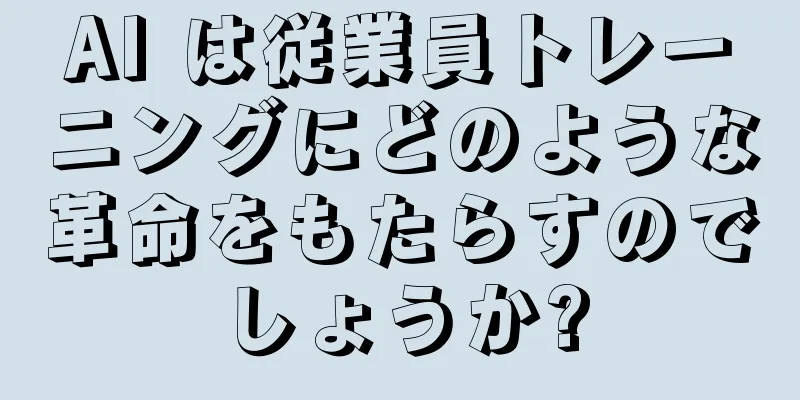工業情報化省がロボット産業の「第14次5カ年計画」を発表:2035年までに指定規模以上の製造業でデジタル化が普及する
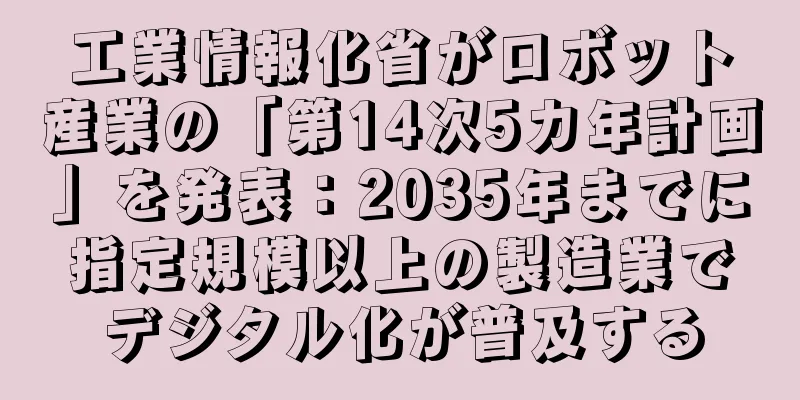
|
12月28日、工業情報化部など各部門は「第14次5カ年計画:インテリジェント製造業発展計画」(以下、「インテリジェント製造計画」という)と「第14次5カ年計画:ロボット産業発展計画」(以下、「ロボット計画」という)を発表した。 「スマート製造計画」では、2025年までに一定規模以上の製造企業のほとんどがデジタル化・ネットワーク化され、重点産業の基幹企業がまずはインテリジェント化を実施し、2035年までに一定規模以上の製造企業でデジタル化・ネットワーク化が全面的に普及し、重点産業の基幹企業が基本的にインテリジェント化を実現するとしている。
「ロボット計画」は、2025年までに中国がロボット技術における世界的なイノベーションの源泉、ハイエンド製造業の集積地、統合アプリケーションの新たな高地となることを提案している。ロボット産業の営業利益は年間20%以上増加し、製造業におけるロボットの密度は2倍になる。 インタビューを受けた専門家によると、各国は製造業の活性化を中核とする「再工業化」戦略を実施しており、インテリジェント製造業の発展に重点を置き、先進製造分野での優位性を継続的に強化しているという。中国も製造業の比率を安定させる必要性を常に強調している。しかし、わが国の製造業企業の知能化レベルは現時点では不均一である。一方では、知能化製造業の応用と推進を階層的かつ段階的に行うべきである。他方では、知能化への転換を加速し、技術の主導権を握り、わが国の知能化製造業の「グローバル化」を推進する必要もある。 主要技術のブレークスルー製造業の質の高い発展今年、「第14次5カ年計画」の概要では初めて「製造業の比率の安定化」が言及された。工業情報化部の肖亜青大臣は最近、雑誌「求是」の中で、わが国の製造業がGDPに占める割合は2006年のピーク時の32.45%から2020年には26.2%に低下したと書いている。製造業の比率があまりに早く、あまりに急速に低下した場合、現在の経済成長を抑制し、都市部の雇用に影響を及ぼすだけでなく、産業の「空洞化」を招き、我が国の経済リスク耐性と国際競争力を弱める可能性もあります。 「スマート製造計画」では、現在の製造供給は市場の需要に対する適応性が高くなく、産業チェーンとサプライチェーンの安定性が課題に直面しており、資源と環境要因の制約が厳しくなっていると指摘しています。 2025年までに供給能力を大幅に強化する必要があり、インテリジェント製造設備と産業用ソフトウェア技術の市場満足度はそれぞれ70%と50%を超えるでしょう。 注目すべきは、「スマート製造計画」が主要なコア技術の研究開発を第一の重点課題として挙げ、それを4つのカテゴリーに分類していることである。第一に、設計シミュレーション、ハイブリッドモデリング、協調最適化などの基礎技術、第二に、積層造形、超精密加工などの先進プロセス技術、第三に、インテリジェント知覚、人間と機械のコラボレーション、サプライチェーンのコラボレーションなどの共通技術、第四に、人工知能、5G、ビッグデータ、エッジコンピューティングなどの産業分野での応用技術です。 CCIDコンサルティングのインテリジェント製造産業研究センターの上級アナリスト、徐英雪氏は、21世紀ビジネスヘラルド紙に対し、基礎技術研究の不足が中国が現在「行き詰まっている」主な理由の一つであると語った。コンピュータシミュレーションソフトウェアCAEを例にとると、現在、欧米先進国のCAEソフトウェアはわが国の市場シェアの90%以上を占めています。中国企業はこの分野での深い探求を始めていますが、海外との差はまだ大きいです。 「計画には『技術』という言葉が頻繁に登場しており、これは我が国が『第14次5カ年計画』期間中に技術の向上に多大な努力を払うことを示すのに十分だ」徐迎雪氏は、高度なプロセス技術の欠如が我が国が「行き詰まっている」もう一つの理由だと考えている。フォトリソグラフィー機を例に挙げましょう。フォトリソグラフィー機はチップ製造における重要な設備であり、その開発には原材料と精度に対する要求が極めて高いです。現在、我が国はフォトリソグラフィー機を独自に開発することができず、その結果、我が国の集積回路産業の発展は長い間、他国に支配されてきました。 さらに、徐英学氏は、共通技術の研究は重複開発や資源の浪費を避け、限られた資源を他の重要な中核技術の研究にさらに投入するのに役立つと述べた。 「スマート製造計画」では、情報インフラの改善、産業インターネット、モノのインターネット、5G、ギガビット光ネットワークなどの新しいネットワークインフラの大規模導入の加速、企業による社内外ネットワークのアップグレードと変革の促進の必要性も言及されている。 27日に発表された「国家情報化第14次5カ年計画」でも、「2025年までに情報化発展レベルを大幅に向上させる」という目標が打ち出され、「ユビキタス・インテリジェント・デジタルインフラシステムの構築」が主要任務のトップに位置付けられ、デジタルインフラ建設の加速と次世代インテリジェント施設システムの適度に進んだ導入が求められている。 徐迎雪氏は、インテリジェント製造は新世代の情報技術によって製造業に力を与え、品質の向上、コストの削減、効率の向上を図ることを目指していると述べた。産業分野における情報技術の応用は、「応用性」という中核原則に基づくべきである。 センスタイム知能産業研究所所長の田鋒氏は21世紀ビジネスヘラルドに対し、中国の現在の「技術インフラ配当」は明らかだと語った。人工知能スーパーコンピューティングセンター、5G基地局、ビッグデータ分析などの技術は世界をリードしており、強力なインフラ能力を通じて、長江デルタ、粤港区、成都・重慶、長江中流域などの製造業集積都市に急速に広がり、スマート製造企業に強力なサポートを提供している。 デジタル・インテリジェント変革の階層的推進工業情報化部は今年4月、早くも「第14次5カ年計画:インテリジェント製造発展」の意見募集草案を発表した。提案された目標は、一定規模以上の製造企業の50%以上がインテリジェント製造能力の成熟度レベル2以上に達し、重点産業と地域の企業の20%以上と15%以上がレベル3以上に到達するというものだった。 28日に正式発表された「スマート製造計画」では、「一定規模以上の製造企業の70%が基本的にデジタル化とネットワーク化を実現し、業界の発展をリードするスマート製造モデル工場を500社以上建設する」と変更され、スマート製造能力の成熟度に対する定量的な要求が引き下げられた。 CCIDコンサルティングが提供するデータによると、2021年12月末現在、全国2万社以上の製造業企業が成熟度自己診断を実施しており、全国31省(市、地域)303都市、31の主要製造業種をカバーしている。全体的に見ると、わが国の製造企業のスマート製造能力の成熟度はまだ比較的低く、レベル1以下の企業が自己診断企業総数の73.26%を占め、レベル2からレベル5の企業数はそれぞれ全体の13.03%、6.53%、3.52%、3.66%を占めています。 これについて、工業情報化部設備産業発展センター政策企画部の左世全主任は、「スマート製造能力成熟度評価方法」が今年5月から実施されていると説明した。スマート製造企業は5つのレベルに分けられ、レベル2は自動化と部分的なデジタル化に重点を置き、レベル3はデジタル化に重点を置き、レベル4以上はインテリジェンスに重点を置く。ただし、各製造業の技術と問題点は異なり、サプライチェーンの連携を促進するには、それらに適応し、実際の状況に合わせて更新される標準が必要である。 「特に中小企業にとって、ある程度のインテリジェント製造基準を満たすことは、基本的な発展ニーズを満たし、良い成果を達成している可能性がある。この場合、いくつかの重要でない基準を満たしていないという理由だけで成熟度が低いと評価されるのは、わが業界の実際の発展に合致しない」と左世全氏は21世紀ビジネスヘラルドに語った。 機械工業計器総合技術経済研究所の欧陽金松所長も、新たに設定された変革目標は、インテリジェント製造能力に対する実際の要求を弱めるものではなく、企業が自己評価を行う上でより役立つだけだと考えている。現在、業界標準はトップダウンのシステムフレームワークを形成している。今後は、各業界、さらには個々の企業が独自の詳細な標準を策定しなければならない。 田鋒氏は、中国は世界最大の製造国だが、世界の利益に占める割合が市場シェアに見合っていないと指摘し、これは、レベルの高い少数の大手企業を除いて、多数のロングテール中小製造企業の成熟度が全体的に低く、その結果、わが国のハイエンド製造業が弱く、中低エンド製造業が広く存在していることを意味すると述べた。 この点について、徐英学氏は、インテリジェント製造の応用と推進は段階的かつ段階的に行うべきだと提案した。大企業は自らのインテリジェンス化を前提に、上流・下流企業間のサプライチェーン連携を推進し、スマートサプライチェーンを積極的に推進するよう努めるべきである。 「リソースが限られている中小企業にとって、研究開発、生産、販売、物流、アフターサービスなどのインテリジェントチェーン全体を網羅する大企業の実証事例は、実際の業務にはあまり参考になりません。」徐迎雪氏は、中小企業にはシナリオや生産ラインなど、より集中した単位に基づいたパイロット実証が必要だと述べた。ソリューションプロバイダーが中小企業の共通ニーズを満たすリソースと機能の共有プラットフォームを構築し、軽量で低コストの標準化されたソリューションを形成できるようにサポートします。 RCEPが発効間近スマート製造業が「グローバル化」中国税関総署のデータによると、中国は8年連続で世界最大の産業用ロボット消費国となっている。しかし、近年、我が国の産業用ロボットの輸出入量は大きく変動しており、2019年に初めて輸出が輸入を上回った後、輸出は減少を続け、輸入は増加を続けています。 2021年1月から9月まで、我が国は87,846台の産業用ロボットを輸入し、43,160台を輸出しました。 CCIDコンサルティングのインテリジェント設備産業研究センターの上級アナリスト、趙海鵬氏は21世紀ビジネスヘラルドに対し、わが国のロボット産業は依然として、主要技術とコア部品の輸入依存、産業基盤の改善の必要性、ハイエンド製品の供給不足、一部の製品が依然として世界の先進レベルと大きな差があるなどの問題に直面していると語った。国内の重要な分野の主要なハイエンドロボット製品は現在、輸入に依存しており、大きな貿易赤字をもたらしている。 注目すべきは、RCEPが来年1月1日に正式に発効することである。こうした背景から、「ロボット計画」と「スマート製造計画」はともに、製品、ソフトウェア、標準、ソリューションの「海外展開」を促進し、ウィンウィンの協力を実現することを提案している。 同時に、最新発表された「2021年版外商投資参入ネガティブリスト」では、2021年版の国家リストが31項目に削減され、自由貿易区のネガティブリストの製造項目がクリアされました。 趙海鵬氏は、わが国の有力ロボット企業は「一帯一路」沿線やRCEPパートナー国の市場を積極的に開拓し、ロボット企業による海外での合併や買収を奨励し、研究開発センターや工業団地などを設立し、海外ロボット生態系マトリックスを構築することで、ロボット製品の生産量をさらに増やす必要があると述べた。 田鋒氏は、複雑で変化する国際情勢と世界の疫病の課題を踏まえ、中国、さらにはアジア太平洋地域の地域インテリジェント製造サプライチェーンの補完と相互支援の再構築は、中国の製造業に多くのチャンスをもたらすだろうと述べた。地域経済貿易協力を通じて、広大な市場を拡大できるだけでなく、地域内の産業チェーンとサプライチェーンを再統合し、インテリジェント製造の連携効率を向上させ、産業チェーンとサプライチェーンの回復力を高めることができます。 |
<<: 2022年までのビッグモデルの未来を展望し、周志華、唐潔、楊紅霞といったビッグネームはどう考えているのだろうか?
>>: AIはローカルアプリケーションから大規模な「AI主導」企業へと進化しました
推薦する
人材獲得におけるAIの台頭
[[405721]]過去 10 年間で採用手法が進化するにつれ、人材獲得における人工知能の活用がます...
AIは物理的なセキュリティ運用に高度な分析を活用しています
人工知能が徐々に物理セキュリティの分野に参入するにつれて、より高度なアクセス制御ソリューションが登場...
EasyDLは、臨床試験データの敵対的学習と複数のアルゴリズムの比較を簡単に処理します。
[51CTO.com からのオリジナル記事] 画像学習は高度なアルゴリズムであり、画像への高い適応...
なぜマスク氏の新しい「脳コンピューターインターフェース」は大きな進歩なのでしょうか?
昨日のマスク氏の発表を見た後、サイバーパンク映画をたくさん思い出し、一晩中夢を見ました。北京時間の昨...
ブロックチェーンが人工知能に力を与える方法
現在、データはデジタル環境に残っており、共有する動機はほとんどありません。これにより、Google、...
TS と AI が出会うと何が起こるでしょうか?
人工知能は日々進歩しており、大規模な言語モデルはますます強力になっています。仕事に役立つ AI ツー...
クラウド上の優れた機械学習サービス
クラウドの優れた機械学習サービスを使用すると、ユーザーはデータをより適切に分析し、新たな洞察を得るこ...
データマイニングの基本概念と最も一般的に使用されるアルゴリズムについての簡単な説明
現在、国民経済と生活のあらゆる分野でビッグデータの理論と応用が盛んに行われています。ビッグデータの基...
マイクロソフトCEOナデラ氏との対談:AIは雇用を奪うよりも多くを創出する
マイクロソフトのCEOに就任して以来、サティア・ナデラ氏はマイクロソフトを改革した英雄とみなされてき...
最も人気のある 5 つの人工知能プログラミング言語の比較。1 つだけでも学ぶ価値があります。
ほとんどのソフトウェア アプリケーション開発と同様に、開発者は複数の言語を使用して AI プロジェク...