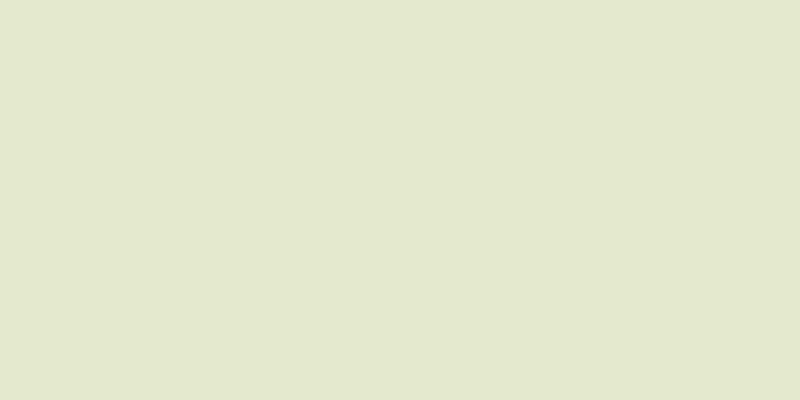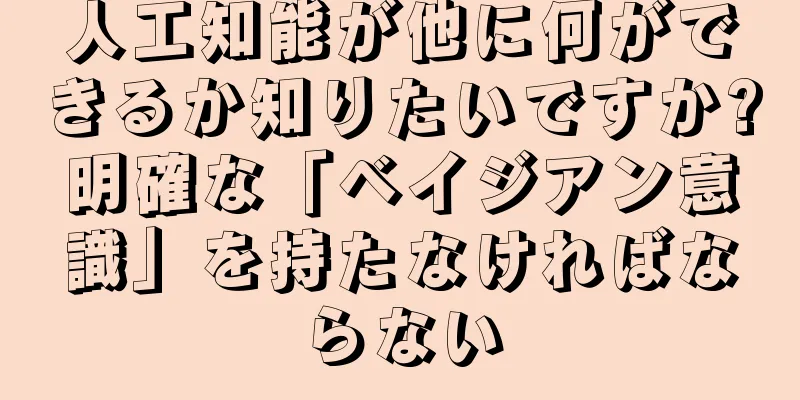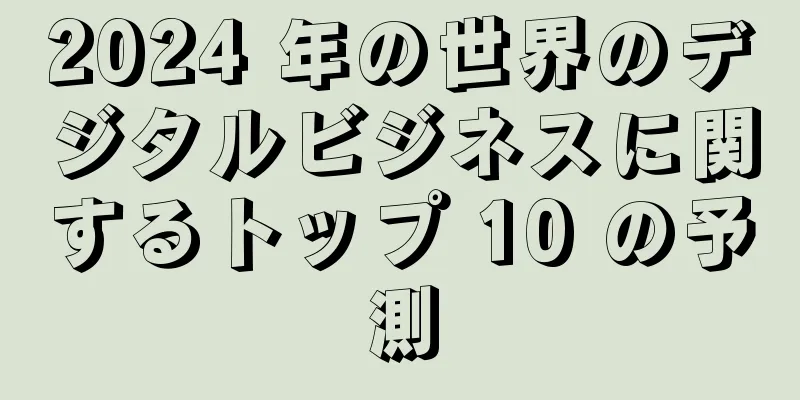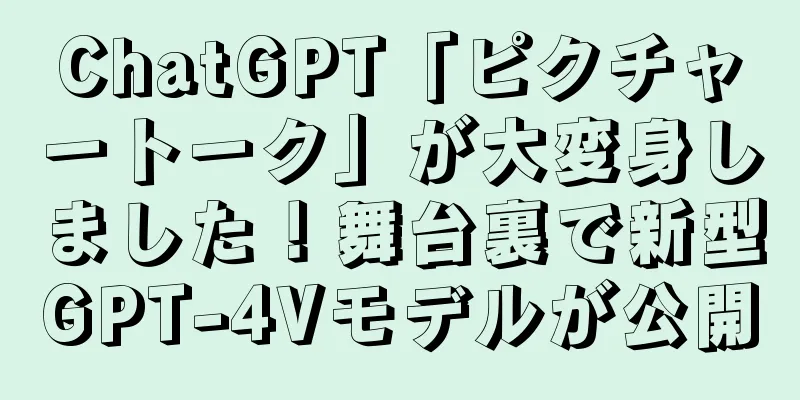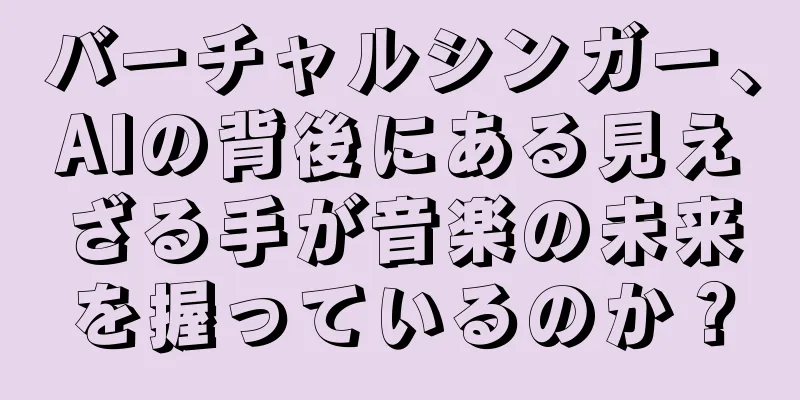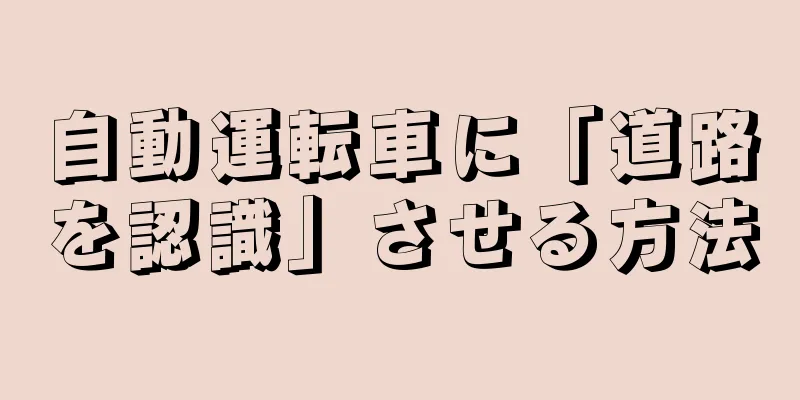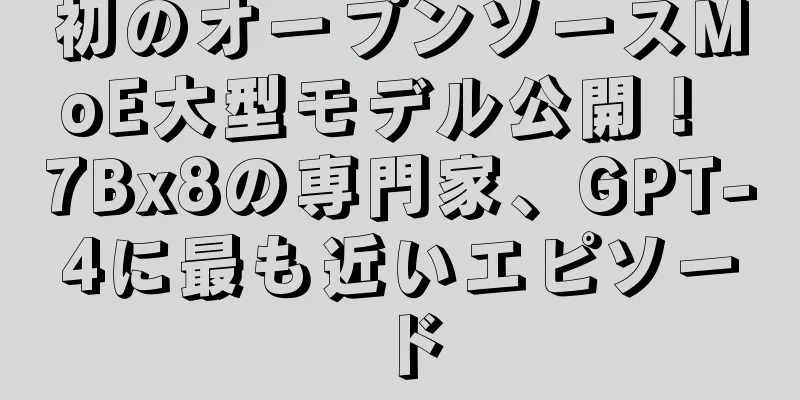70%は輸入品。中国の産業用ロボットはチップのような悲劇をどう回避できるのか?
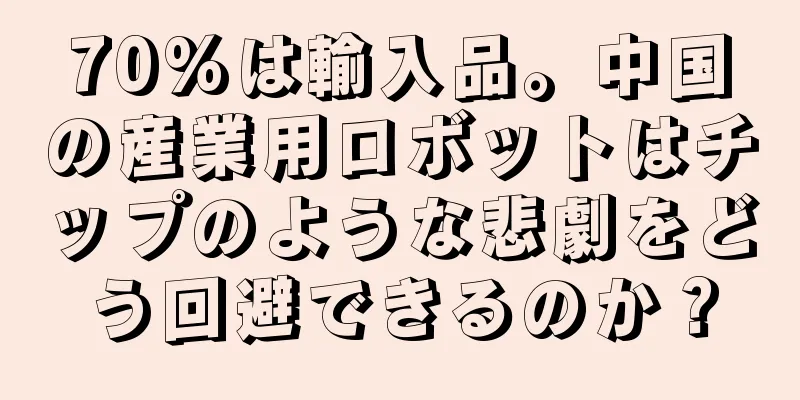
|
ロボットは産業の魂です。
しかし、私たちの身近な国である日本が、20年もの間、世界の産業用ロボット市場を支配し、数え切れないほどの産業メーカーの首を絞めてきたことを知る人はほとんどいません。日本が供給を遮断すれば、多くの工業生産が停止の危機に瀕するだろう。 1. 日本のロボットが世界を席巻 ロボット分野のトップ4社は、業界の「四大ファミリー」として知られています。日本のファナック、スイスの安川電機、スイスのABB、ドイツのKUKAです。 これら4大ファミリーを合わせると、わが国の産業用ロボット市場の70%以上、世界の産業用ロボット市場のほぼ半分を占め、圧倒的な優位性を持っています。 ▲2020年中国市場産業用ロボットブランド売上ランキング 高級自動車、チップ、電子機器に使用される6軸多関節ロボットなど、一部の高級産業用ロボット分野では、4大ファミリーが中国市場の90%以上を直接占めており、国内メーカーにはほとんど抵抗する力がありません。 そのうち、日本だけで四大宗派の議席の半数を占めています。日本のファナックは2008年に世界で初めてロボット生産台数20万台を突破したメーカーとなり、その市場シェアは世界一を維持している。 2000年以降、日本は強力な産業用ロボットの研究開発および生産能力を活かして、世界最大の産業用ロボットの生産国および輸出国になりました。 2019年、貿易摩擦と深刻な感染症情勢の二重の影響下でも、日本の産業用ロボットの輸出額は依然として159.2億ドルに達し、欧米諸国をはるかに上回り、ロボット産業の分野ではまさに「超大国」となった。 対照的に、我が国では、産業労働者1万人あたりの産業用ロボットの数はわずか140台で、日本の327台よりもはるかに少ないです。 さらに恐ろしいのは、産業用ロボットの上流生産の中核部品も日本が独占していることだ。 精密減速機を例に挙げると、これはロボット関節の主要部品であり、ロボットの総コストの約40%を占めています。これは最も重要な部品の1つであり、「ロボットの最高の宝石」と呼ばれています。 この分野でも日本企業は圧倒的な優位性を持っています。 世界の減速機市場は、ナブテスコ、ハーモニック、住友、シンポなどの日本企業によって独占されています。日本の企業が市場を独占しており、「ビッグフォー」の家族でさえ日本から購入しています。 ▲日本の基幹ロボット部品産業の優位性、出典:戴栄栄著『日本の産業用ロボットの台頭』 減速機は精密機械技術の最高峰であり、技術的敷居が非常に高く、材料科学、精密加工装置、組立技術などの分野の集大成であり、長期間の経験の蓄積が必要であり、カーブでの追い越しはほとんど不可能です。 「産業の魂」である産業用ロボットの台頭は、日本の強力な工業生産と密接に関係しています。 日本はアメリカ、ドイツに次いで工作機械産業を確立した世界で3番目の製造大国です。第二次世界大戦後、日本政府は国内の工業生産を積極的に支援しました。戦略的には、貿易と科学技術を基盤とした国家の建設を提唱し、戦術的には、鉄鋼、自動車、電力、半導体、原子力などの重工業の支援に重点を置きました。1982年以来、日本は長きにわたって世界有数の工業大国となっています。 日本の自動車業界では1970年代後半から産業用ロボットの実験が始まり、1980年代には大規模な普及段階に入った。統一された機械組立ライン生産により、日本の自動車メーカーはコストが下がり続けながら急速に成長することが可能になった。 今日、日本の自動車メーカーが世界を支配していることは誰の目にも明らかです。トヨタ、ホンダ、日産の収益を合わせただけでも1,000億ドルを超えます。 2018年、自動車産業は日本の工業生産高の40%を占めました。 1970年代後半、日本の半導体産業は急成長を遂げ、世界シェアは10%から40%に急上昇し、米国から異常なほどの弾圧を受けるほどだった。 半導体チップの上流設備や材料の分野では日本企業が絶対的な発言力を持っている。半導体産業全体の主要材料19種のうち、14種については日本企業が世界市場の半分以上を独占している。 四大ファミリーの一つである安川電機は、半導体製造に産業用ロボットを応用した世界初のロボット企業でもある。 急成長を遂げる製造業と、高齢化が進む日本社会の対照をなすのが、労働力の需給矛盾が深刻化する中、日本の産業用ロボットが急成長し、優位に立とうとしている。 2. 40年前の国家戦略 1970年、戦後のベビーブームが徐々に終焉を迎え、65歳以上の高齢者人口の割合が7%を超え、日本は高齢化社会に突入しました。 しかし、この頃、日本社会は戦後の奇跡的な経済発展という、歴史上前例のない出来事を経験していました。 第二次世界大戦の終結後、日本の国家経済は致命的な打撃を受け、国の富の40%が戦争で破壊され、経済は大きく崩壊し、社会は混乱状態が続きました。 しかし、日本政府は戦後の国際貿易の急増という好機を捉え、国内に前例のない工業化の波を起こしました。国民の富裕層が急速に増加し、わずか20年余りで経済は急成長しました。 1965年から1970年にかけて、日本経済は超好景気期に入り、工業生産額の年間平均成長率は16%に達し、GDP成長率は11%を超えました。1968年にはドイツを抜いて、米国、旧ソ連に次ぐ世界第3位の国となりました。 この神話的な経済的繁栄は、日本人によって神にちなんで「イザナギ景気」と呼ばれました。 しかし、高齢化は日本の産業界にとって悩みの種となっている。 ▲1954年から1984年までの日本のGDPと労働力の対比、出典:中国銀河証券研究所 1970年、日本の造船、テレビ、半導体ラジオの生産は世界第1位となり、鉄鋼、自動車、肥料、合成繊維の生産はアメリカに次ぐ第2位でした。 しかし、当時の日本の生産年齢人口はわずか5,153万人で、前年比増加率は1%未満でした。 急増する産業需要と高齢化の進行により大きな労働力不足が生じ、日本の製造業では人材不足が続き、コストが急上昇しています。 同時に、日本の産業の急速な発展により、米国の「経済大国」としての地位が脅かされ始め、日米間の貿易摩擦は激化の一途をたどった。
▲ニクソンが当選 1968年、ニクソンは大統領選挙で日本の繊維産業の抑制を公約し、日米間の最初の保護貿易戦争の幕が正式に開いた。 大きな貿易黒字、ますます不利になる貿易環境、急激な円高により、日本政府は国家の位置づけを再検討し、「貿易立国」から「技術立国」へと正式に転換することを余儀なくされ、技術革新の重要性がかつてないレベルに高まっています。 この頃、日本は積極的に海外の先進技術を導入し始めました。これらの技術は、模倣から革新へ、模倣から凌駕へと進み、やがて日本社会に徐々に定着し、日本の産業革新の礎となりました。 海の反対側では、アメリカの会社ユニメーションが 1959 年に世界初の産業用ロボットを開発しました。同社の創設者であるジョセフ・エンゲルバーガーは、業界から「ロボット工学の父」として称えられました。 1969年、日本の川崎重工業はユニメーションの技術を導入し、日本史上初の産業用ロボット「ユニメート」の開発に先駆け、日本の産業用ロボットの先例を築きました。
▲ユニメーション社初の産業用ロボット 画像提供:川崎重工業 当時のロボットはまだ開発の初期段階にあり、大きくてかさばり、非常に単純な作業しかこなせず、指標も未成熟でした。 しかし、日本国内の極度の人手不足を背景に、ロボットは急速に実用化段階に入り、ユニメーションの基盤である自動車製造の分野で最初に活用され、機械、電子などの製造業へと急速に拡大しました。 日本政府も手をこまねいてはいませんでした。産業用ロボットに対する一連の優遇政策を導入したほか、1971年と1978年には「メカトロニクス法」と「機械環境法」を迅速に公布し、ロボット産業の業界基準の策定と改善を主導し、ロボットの大規模応用への道を開きました。 一方で、日本は技術導入に留まらず、技術研究開発に多額の投資を行い、世界初の国立ロボット協会を設立しただけでなく、世界初のアーク溶接ロボット、世界初のスカラ型産業用ロボット、世界初のモーター駆動型ロボットなどを独自に開発しました。
▲1980年代の自動車生産ラインで活躍する川崎重工業の産業用ロボット 画像提供:川崎重工業 1980年、日本は企業による産業用ロボットのリースを促進するため、2つの法律を公布しました。日本の財務省、日本政策投資銀行、および24の産業用ロボット企業が主導して「日本ロボットリース株式会社」を設立し、中小企業にロボットのリースと融資を提供し、産業チェーン内の大企業、中堅企業、中小企業の工場にロボットを導入しました。 一連の狂気じみた減税、補助金、ローン割引、制度的傾斜などの支援を受けて、日本の産業用ロボットは活発な発展の第一波を迎えた。 1970年、日本の産業用ロボットの年間生産台数は約1,350台でしたが、1980年には19,843台に急増し、年間平均成長率は30%を超えました。 「技術立国」の波を受け、日本社会はロボット技術を積極的に吸収し、川崎重工業、安川電機、ファナックなど数多くの産業用ロボットが登場し、あっという間に国内市場を席巻しました。 それ以来、日本のロボット産業は「技術輸入」の規制を完全に撤廃し、爆発的な成長を遂げた黄金の20年を迎えました。 1982年、日本のロボット保有数は10万台を超え、先進的なロボット保有数は世界全体の56%以上を占め、ロボット技術発祥の国である米国を大きく上回りました。 1990年代以降、ファナックと安川電機が世界トップクラスの産業用ロボットメーカーとして台頭しました。日本国内の市場が飽和状態になる中、政府の積極的な指導のもと、日本のロボットメーカーが海外市場に本格的に進出し始めている。 日本国内の市場規模は世界市場とは比べものにならないほど大きく、安価で精密かつ制御性に優れた日本の産業用ロボットは瞬く間に世界中で認められ、注文が殺到した。 2012年、日本のロボット輸出は業界全体の売上高の70%以上を占め、巨大で成長を続けるアジア市場は日本製ロボットの最大の買い手となった。 2000年以降、日本は世界最大のロボット大国へと成長しました。ロボットの生産・販売でトップの座を確固たるものにしているだけでなく、減速機やサーボモーターなど上流の基幹部品もコントロールしており、ロボット界のリーダーと言えるでしょう。 3. 中国の追い上げへの道 中国経済が引き続き上昇するなか、米中貿易情勢は悪化し始め、国内の出生率は低下し、人口ボーナスは徐々に消滅し、企業の人件費は上昇し続けている... すべてが過去の日本の市場と非常に似ています。 実際、中国は1980年代の日本が経験したのと同様の産業用ロボットの需要の急増に直面しています。 2013年以来、中国は世界最大の産業用ロボット市場となっている。 2016年、中国のロボット総設置量は前例のない発展速度で驚異的な世界第1位に達しました。 しかし、我が国の産業用ロボットの生産・製造能力は非常に遅れており、コア技術とコア部品によって「窒息」しているだけでなく、ハイエンドロボット市場は完全に失われる危機に瀕しています。 その理由も40年前に遡ります。 1977年、日本社会がロボットを積極的に受け入れ始めた頃、湾岸の向こう側にある中国はまだ産業探査の第一歩を踏み出していませんでした。 このとき、中国のロボット産業における最も重要な人物の一人であり、将来の学者であり「中国ロボットの父」と呼ばれる蒋欣松が人々の目に留まりました。
▲学士 江新松 1977年、多くの国がロボット産業に多額の投資をしました。東北工業オートメーション研究所での長年の研究経験から、江新松はロボットが国の科学技術力と産業レベルの象徴となることを痛感しました。 その年の中国科学院自然科学企画会議で、江新松氏は初めてロボットと人工知能の開発のアイデアを提案し、その後「海洋における知能ロボットの応用」などの重要なテーマを提案した。 しかし、「動乱の10年」は中国の科学技術界に深刻なダメージを与えた。多数の科学者が迫害され、科学研究は完全に停滞しており、人材、資金、技術の不足により、国際的な先進レベルに追いつくのは容易ではありません。 中国が主任設計者の蒋欣松氏の指揮の下、初めて機能する水中ロボット「海燕1号」を製作したのは1985年になってからだった。
▲「シーマン1号」ロボット画像出典:CCTV 8年間の努力を経て、「シーマン1号」の成功は、中国のロボット産業研究が新たな段階に入ったことを示すだけでなく、江新松氏や他の科学者たちの自信を大きく高めた。 1986 年 3 月、ロボット工学プロジェクトが我が国の「863 計画」(国家ハイテク研究開発計画) に組み込まれ、世界の科学技術の最先端に到達するための戦いが始まりました。 その後、江新松氏は「863計画」の自動化分野の主任科学者として4期連続で再選されただけでなく、チームを率いて我が国のCIMS、特殊ロボット、知能ロボットなどの分野のギャップを克服し、「ロボット工学入門」を編集・執筆し、中国自動化学会の出版物「情報と制御」と「ロボット」誌を創刊し、我が国のロボット産業の発展を全面的に推進しました。 1994年、江新松は中国工程院の最初の院士の一人に選出された。彼は1997年に66歳で突然の心臓発作で亡くなった。 江新松氏を記念して、現在中国最大かつ世界トップクラスの新松ロボット会社に彼の名前が付けられました。
現在、我が国の産業用ロボット産業は40年の歴史を誇り、いくつかの分野では画期的な進歩があったものの、全体的な発展は常に遅れをとっています。 中国の改革開放が深まるにつれ、同国の工業製造能力は向上し続け、産業用ロボットの需要は増加し続けています。2013年以来、中国は世界最大の産業用ロボット市場となっています。 華創証券のデータによると、現在、わが国における産業用ロボットの国産化率は30%未満で、国内大手企業の市場シェアは3%未満です。 コア部品に関して言えば、現在、国内減速機市場の約85%、サーボモーター市場の70%、コントローラー市場の80%以上が海外ブランドによって占められており、ハイエンドの製品ラインは完全に失われ、多くのギャップがあります。 中国工業経済連合会会長で元工業情報化部長の李一中氏はかつて、「わが国は今や工業大国ではあるが、工業大国ではない。製造大国ではあるが、製造大国ではない。そのギャップと欠点をはっきりと認識しなければならない」と嘆いた。 1980年代の日本と比べると、米国の抑圧、人口の高齢化、人件費の上昇、産業需要の増大、技術輸入への長期依存など、類似点が多すぎます... ▲我が国の製造業の人件費は上昇し続けている 画像提供: デボン研究所 違いは、中国の広大な市場空間が国内のロボットメーカーにより多くの開発機会を提供していることです。 「国産代替」の巨大な波の下、新エネルギー車、チップ半導体、ハイテク電子などの新興産業が生み出した市場需要に伴い、2020年の産業用ロボットの国内生産台数は合計23万台に達し、前年比19.1%増加した。12月だけでも2万9000台を超え、過去最高を記録した。 パンデミック後の時代において、中国は経済を適切にコントロールし、業務と生産の再開に成功した数少ない国の一つとして、製造業の需要の急増をもたらしました。 中国投資産業研究院の「2021~2025年中国ロボット産業投資分析及び展望予測レポート」によると、中国のロボット市場の今後5年間の平均年複利成長率は約15.80%となり、2025年には市場規模が1,463億元に達すると予想されています。 世界は広く、やるべきことはたくさんあります。 |
推薦する
フェイフェイ・リーのチームの新しい研究:脳制御ロボットが家事を行い、脳コンピューターインターフェースに少ないサンプルで学習する能力を与える
将来的には、考えただけでロボットに家事を任せることができるようになるかもしれません。スタンフォード大...
MonoLSS: 視覚的な 3D 検出トレーニングのためのサンプル選択
この記事は、Heart of Autonomous Driving の公開アカウントから許可を得て転...
人工知能は核爆弾と同じくらい人類にとって脅威なのでしょうか? AI脅威理論の謎を解く
新たに世界一の富豪となり、テスラのCEO、そしてテクノロジー界の大物となったマスク氏は、ロボットが近...
もしエイリアンが本当に存在するなら、AIは最終的に彼らを見つけるだろう
この記事は公開アカウント「Reading Core Technique」(ID: AI_Discov...
ロボットの時代が来ます。私たちは全員失業してしまうのでしょうか?
[[415590]]ボストン・ダイナミクス社が開発したヒューマノイドロボット「アトラス」、ロボット...
GPUベースの人工知能と機械学習アプリケーション
[51CTO.com クイック翻訳]今日、グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) は、...
スタンフォード大学、AIがシマウマを犬と誤認する理由を発見
この記事はAI新メディアQuantum Bit(公開アカウントID:QbitAI)より許可を得て転載...
Googleのジェフ・ディーンの返答は計画を覆した。リー・フェイフェイの教え子ティムニットは解雇されたのではなく、自らの意志で辞職したことが明らかになった。
先週、Googleのアフリカ系アメリカ人倫理学者ティムニット・ゲブル氏の「解雇」がTwitterやR...
スマートフォンの代替品?元アップルデザイナーが699ドルの人工知能ブローチ「AI Pin」を発売
海外メディアの報道によると、元アップルのデザイナー、イムラン・チャウドリ氏とベサニー・ボンジョルノ氏...
AI、メタバース、職場におけるDEI
AI とメタバースが仕事を変えるにつれて、リーダーは DEI に影響を与える新興テクノロジーの 3...